不動産の生前贈与と売却どちらが得?税金・費用・手続きを徹底比較
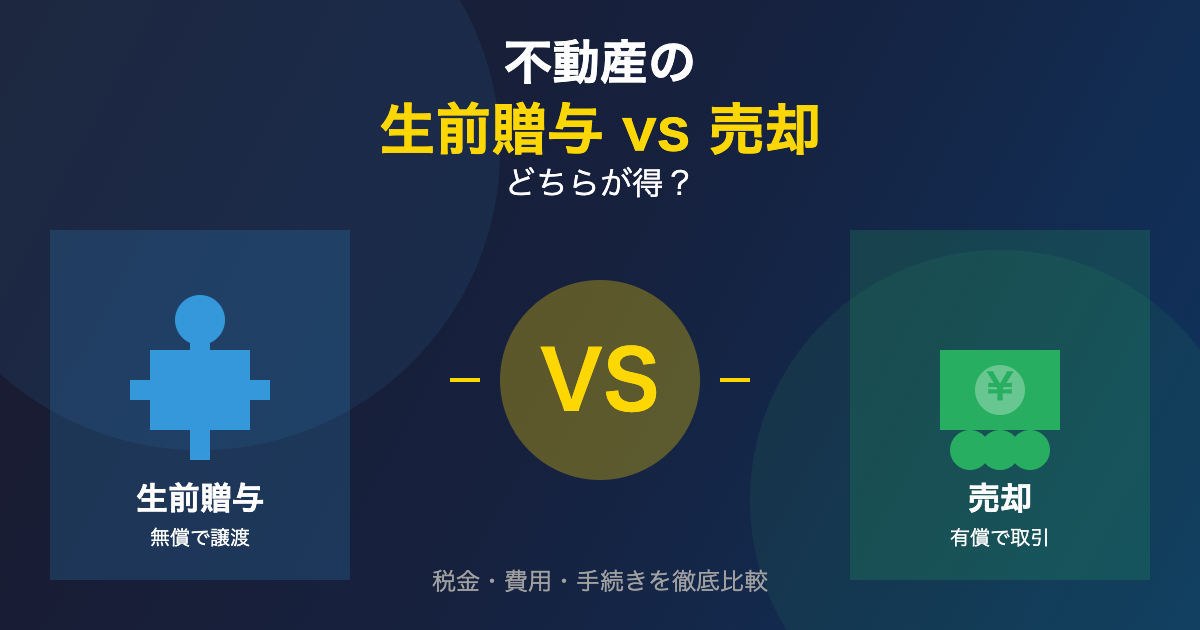
📑 目次
不動産の生前贈与と売却どちらが得?税金・費用・手続きを徹底比較
親が所有する不動産を子供に引き継ぐ方法として、「生前贈与」と「売却」という2つの選択肢があります。どちらを選ぶかによって、かかる税金や手続き、将来的なメリット・デメリットが大きく異なります。
本記事では、生前贈与と売却の違いを税金・費用・手続きの面から徹底比較し、どのようなケースでどちらを選ぶべきかを詳しく解説します。相続税対策を考えている方、親の不動産を引き継ぐ予定の方は必見です。
生前贈与 VS 売却
生前贈与と売却の基本
生前贈与とは
生前贈与とは、財産の所有者が生きている間に、無償で財産を譲渡することです。不動産の場合、親から子へ所有権を移転し、子が贈与税を負担します。
生前贈与の特徴
- 無償譲渡:対価を受け取らずに不動産を譲る
- 贈与税の発生:受け取った側(受贈者)が贈与税を支払う
- 相続税対策:将来の相続財産を減らすことができる
- 早期の資産移転:親が元気なうちに確実に譲渡できる
売却とは
売却とは、不動産を市場価格または親子間で合意した価格で売買することです。親が売却代金を受け取り、子が購入資金を準備する必要があります。
売却の特徴
- 有償取引:対価を支払って不動産を取得
- 譲渡所得税の発生:売った側(親)が譲渡所得税を支払う
- 購入資金が必要:子が住宅ローン等で資金調達
- 市場価格に近い取引:適正価格での売買が必要
🎁 生前贈与
💰 売却
かかる税金の比較
生前贈与と売却では、かかる税金の種類と金額が大きく異なります。これが選択の最も重要なポイントです。
生前贈与でかかる税金
| 税金の種類 | 課税対象 | 税率・金額 | 支払う人 |
|---|---|---|---|
| 贈与税 | 贈与された財産の価値 | 10〜55%(累進課税) | 子(受贈者) |
| 不動産取得税 | 固定資産税評価額 | 土地3%、建物3% | 子(受贈者) |
| 登録免許税 | 固定資産税評価額 | 2% | 子(受贈者) |
⚠️ 贈与税の計算例
評価額3,000万円の不動産を贈与した場合(直系尊属からの贈与)
- 課税価格:3,000万円 - 基礎控除110万円 = 2,890万円
- 贈与税額:2,890万円 × 50% - 250万円 = 約1,195万円
※実際の税額は、他の特例や控除により変動します
売却でかかる税金
| 税金の種類 | 課税対象 | 税率・金額 | 支払う人 |
|---|---|---|---|
| 譲渡所得税・住民税 | 売却益(譲渡所得) | 短期39.63%、長期20.315% | 親(譲渡者) |
| 不動産取得税 | 固定資産税評価額 | 土地3%、建物3% | 子(購入者) |
| 登録免許税 | 固定資産税評価額 | 2%(所有権移転) | 子(購入者) |
💡 譲渡所得税の計算例
取得費2,000万円、売却価格3,000万円の場合(長期譲渡)
- 譲渡所得:3,000万円 - 2,000万円 - 諸費用 = 約900万円
- 譲渡所得税:900万円 × 20.315% = 約183万円
※居住用財産の特別控除(3,000万円)が使える場合、税金はほぼゼロになります
※概算です。実際の税額は個別の状況により異なります
メリット・デメリットの比較
生前贈与のメリット・デメリット
✅ メリット
- 相続税対策になる:生前に財産を移転することで相続財産を減らせる
- 確実に譲渡できる:親が元気なうちに確実に子に渡せる
- 資金準備不要:子が購入資金を用意する必要がない
- 暦年贈与の活用:毎年110万円まで非課税で贈与できる
- 相続トラブル回避:事前に財産分与を明確にできる
❌ デメリット
- 贈与税が高額:累進課税で最高55%と非常に高い
- 登録免許税が高い:売買の5倍(2% vs 0.4%)
- 不動産取得税がかかる:固定資産税評価額の3%
- 小規模宅地等の特例が使えない:相続時の評価減が適用されない
- 取得費が引き継げない:将来子が売却する際、取得費が贈与時の評価額になり税負担増
売却のメリット・デメリット
✅ メリット
- 税金が比較的安い:特に3,000万円控除が使える場合
- 登録免許税が安い:0.4%(贈与の2%より大幅に安い)
- 取得費を引き継げる:親の取得費を引き継げるため、将来売却時の税負担が軽減
- 住宅ローン控除が使える:子が住宅ローンを組めば控除が適用
- 親に現金が入る:親が老後資金として活用できる
❌ デメリット
- 購入資金が必要:子が資金を用意できない場合は実行不可
- 住宅ローン審査が必要:ローンを組む場合、審査に通る必要がある
- 相続税対策効果が限定的:親に現金が残るため相続財産は減らない
- 著しく低い価格は贈与とみなされる:時価より大幅に安いと贈与税が課税される
- 親子間売買の制約:住宅ローン控除の適用に制限がある場合も
費用の比較
税金以外にも、登記費用、手数料、評価費用などがかかります。
| 費用項目 | 生前贈与 | 売却 |
|---|---|---|
| 司法書士報酬 | 5〜10万円 | 5〜15万円 |
| 不動産鑑定評価 | 20〜30万円(必要な場合) | 20〜30万円(必要な場合) |
| 仲介手数料 | なし | 売却価格×3%+6万円+消費税 |
| 住宅ローン事務手数料 | なし | 借入額×2%程度 |
| 印紙税 | 2万円 | 1〜6万円(売買価格により変動) |
手続きの流れ
生前贈与の手続き
⏱️ 目安期間:手続き完了まで1〜2ヶ月
売却の手続き
⏱️ 目安期間:手続き完了まで1〜3ヶ月(ローン審査含む)
どちらを選ぶべきか?判断基準
(貯金 or 住宅ローンを組める)
(3,000万円特別控除が使える)
税負担が最小限&取得費引継ぎ可能
(相続財産が基礎控除を超える)
暦年贈与や相続時精算課税制度を活用
小規模宅地等の特例が使える可能性
ケース別おすすめの選択
状況:親が現在居住中の自宅(評価額3,000万円)を子に譲りたい。子は住宅ローンを組める。
おすすめ:売却
- 親に居住用財産の3,000万円特別控除が適用できる
- 譲渡所得税がほぼゼロになる可能性が高い
- 子は住宅ローン控除も利用可能
- 登録免許税も贈与の1/5で済む
状況:親が投資用不動産を複数所有。相続財産が基礎控除を大幅に超える見込み。
おすすめ:計画的な生前贈与
- 相続時精算課税制度を利用(2,500万円まで非課税)
- または暦年贈与で毎年110万円ずつ贈与
- 将来の相続税負担を軽減
- 複数の子に分散して贈与することも可能
状況:子に購入資金がない。相続財産は基礎控除内に収まる見込み。
おすすめ:相続まで待つ
- 相続時に小規模宅地等の特例(最大80%減額)が使える
- 相続税がかからないまたは少額で済む
- 贈与税の高額な負担を避けられる
- 親の介護などで同居する可能性も考慮
よくある失敗例と対策
失敗例1:著しく低い価格で売却し、贈与とみなされた
親子間で相場の半額程度で売買したところ、税務署から「低額譲渡」として差額に贈与税が課税されたケース。
対策:親子間売買でも適正価格(時価の80%以上)で取引しましょう。不動産鑑定士の評価書を取得するとより安全です。
失敗例2:贈与税の試算をせずに贈与してしまった
評価額3,000万円の不動産を贈与し、後から1,000万円以上の贈与税が課税されることを知り、支払いに困窮したケース。
対策:贈与実行前に必ず税理士に相談し、正確な税額を試算しましょう。支払えない金額なら別の方法を検討すべきです。
失敗例3:取得費の引継ぎを考慮しなかった
贈与で取得した不動産を数年後に売却したところ、親の取得費を引き継げず、高額な譲渡所得税が発生したケース。
対策:将来子が売却する可能性がある場合、親子間売買で取得費を引き継ぐ方が有利です。長期的な視点で判断しましょう。
活用できる特例・制度
生前贈与で使える制度
1. 暦年贈与
毎年110万円まで非課税で贈与できる制度。不動産の持分を少しずつ贈与することで、贈与税を抑えられます。
- 毎年の基礎控除:110万円
- 長期的な計画で実行
- 複数人への贈与も可能
2. 相続時精算課税制度
60歳以上の親から18歳以上の子への贈与で、2,500万円まで非課税。ただし相続時に贈与財産を相続財産に加算。
- 特別控除:2,500万円
- 一度選択すると暦年贈与に戻れない
- 相続税対策にはならない
売却で使える制度
1. 居住用財産の3,000万円特別控除
自宅を売却する場合、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる。親が自宅を子に売却する場合に有効。
- 控除額:最高3,000万円
- 所有期間の制限なし
- 親族間でも適用可能(同居していない場合)
2. 住宅ローン控除
子が住宅ローンを組んで購入する場合、年末ローン残高の0.7%を最長13年間控除できる。
- 控除率:0.7%
- 期間:最長13年
- 親子間売買でも一定の条件下で適用可能
専門家への相談が重要
生前贈与と売却のどちらを選ぶかは、個別の状況によって最適解が異なります。以下の専門家に相談することをおすすめします。
相談すべき専門家
- 税理士:税金の試算、申告手続き、節税対策のアドバイス
- 司法書士:登記手続き、書類作成のサポート
- 不動産鑑定士:適正価格の評価、鑑定書の作成
- ファイナンシャルプランナー:総合的な資産設計、相続対策
- 弁護士:相続トラブルの予防、遺言書作成
Q&A:よくある質問
Q1:親子間売買で住宅ローンは組めますか?
A:金融機関によっては親子間売買でも住宅ローンを組めますが、審査は厳しくなります。適正価格での取引であることを証明する書類(不動産鑑定書など)が必要になる場合があります。
Q2:生前贈与した不動産は相続財産に含まれますか?
A:相続開始前3年以内の贈与は、相続財産に加算されます(生前贈与加算)。ただし、2024年以降は段階的に7年以内に延長されます。
Q3:贈与契約書は必ず作成すべきですか?
A:法的には口頭でも成立しますが、税務上のトラブルを避けるため、必ず書面で作成しましょう。日付、贈与する財産、贈与者・受贈者の署名押印が必要です。
Q4:不動産を分割して少しずつ贈与できますか?
A:可能です。持分を毎年少しずつ贈与することで、暦年贈与の基礎控除(110万円)を活用できます。ただし、計画的贈与とみなされないよう注意が必要です。
Q5:どちらも選ばずに相続まで待つ方が得な場合は?
A:相続財産が基礎控除内に収まる場合や、小規模宅地等の特例で評価額を大幅に減額できる場合は、相続まで待つ方が得なケースが多いです。
まとめ:それぞれに最適な選択を
生前贈与と売却、どちらが得かは一概には言えません。税金、費用、家族の状況、将来の計画など、総合的に判断する必要があります。
選択のポイント
- 税金を正確に試算する:必ず専門家に相談して試算を
- 長期的な視点で考える:将来の売却可能性も考慮
- 家族全員で話し合う:相続トラブル防止のため事前に共有
- 特例・控除を最大限活用:使える制度を見逃さない
- 書面を残す:契約書、評価書など証拠を必ず保管
大切な不動産をどのように次世代に引き継ぐか。早めに計画を立て、専門家のアドバイスを受けながら、最適な方法を選択しましょう。
🏠 空き家・訳あり物件のご相談はオッティモへ
創業35年の実績と信頼。全国どこでも対応いたします。
生前贈与・売却のご相談、税金シミュレーションまで、まずは無料相談からお気軽にどうぞ。
📞 無料相談はこちら
📱 電話で相談する 💬 LINEで相談する ✉️ チャットで相談する❓ よくある質問(FAQ)
空き家を売却する際に必要な書類は何ですか?
空き家を売却する際には、以下の書類が必要です:
- 登記済権利証または登記識別情報
- 固定資産税納税通知書
- 建物の図面や測量図
- 身分証明書
査定にはどのくらいの時間がかかりますか?
通常、現地調査を含めて1〜3営業日で査定結果をご報告いたします。お急ぎの場合は、最短即日での査定も可能です。



