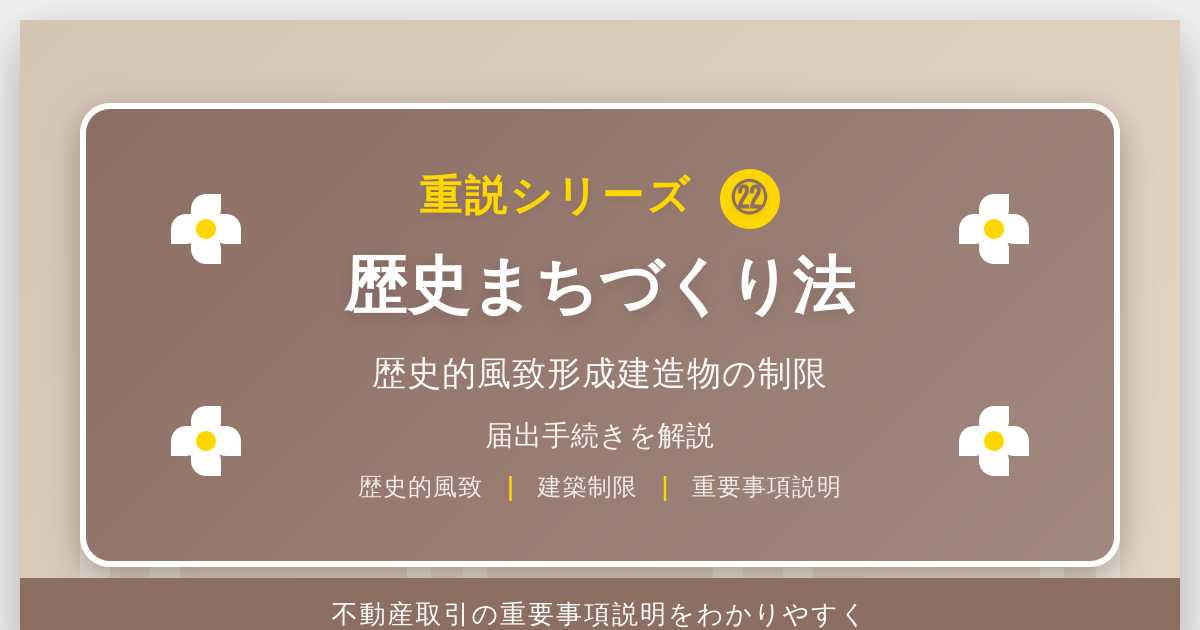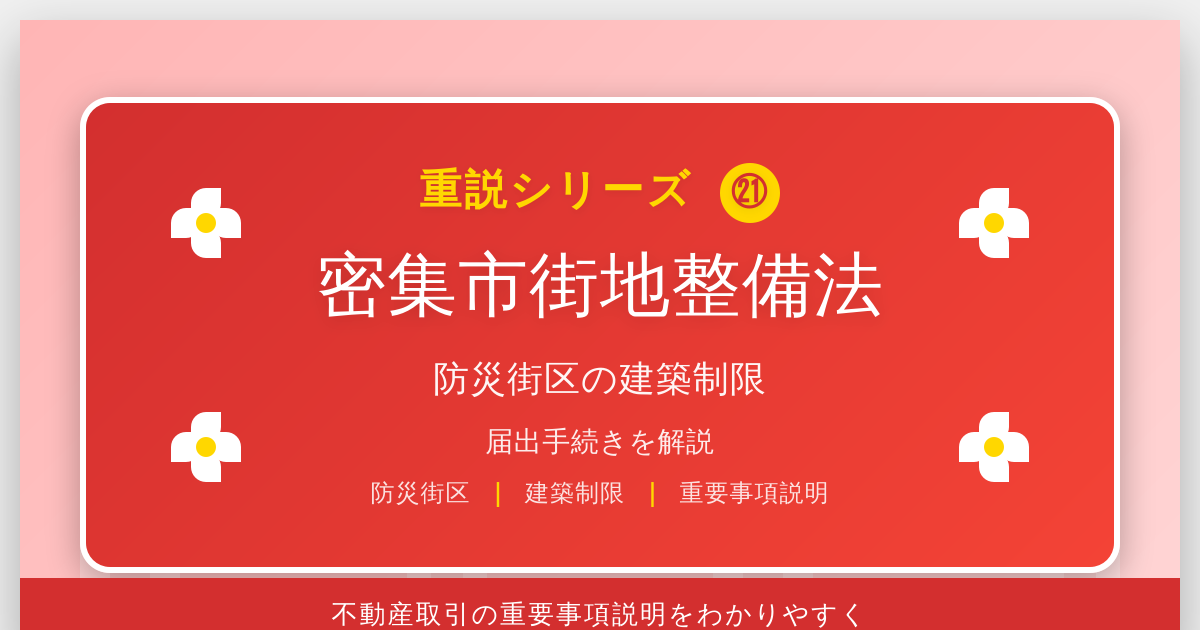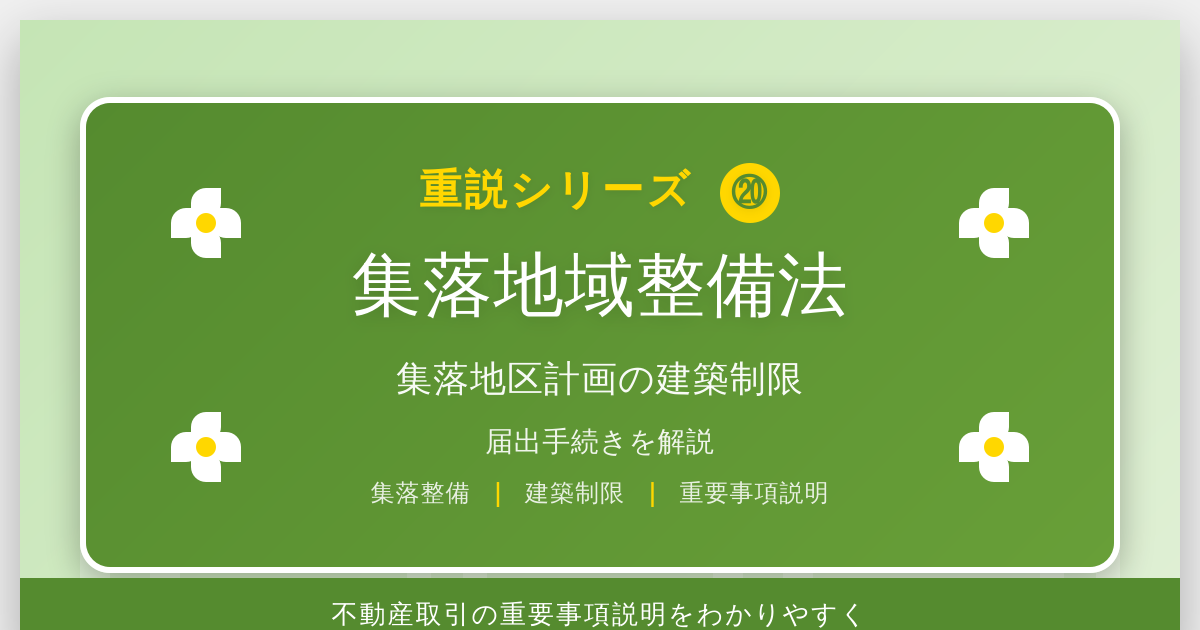建築基準法とは?建ぺい率・容積率をわかりやすく解説|重説シリーズ②

不動産購入で必須の建築基準法を徹底解説!建ぺい率・容積率の計算方法から前面道路制限、高さ制限、接道義務まで、具体例とイラストでわかりやすく説明します。重要事項説明で確認すべきポイントも網羅。
📑 目次
「建ぺい率60%ってどういう意味?」「容積率200%ならどのくらいの家が建つの?」
不動産を購入する際、必ず耳にするのが建築基準法による制限です。この法律は、建物の安全性を確保し、良好な市街地環境を保つために、建物の大きさや高さなどを細かく規制しています。
本記事では、不動産取引における重要事項説明で必須となる建築基準法について、建ぺい率・容積率を中心にわかりやすく徹底解説します。
建築基準法とは?その目的と役割
建築基準法は、建築物の敷地、構造、設備および用途に関する最低基準を定め、国民の生命・健康・財産の保護を図る法律です。
🏗️ 建築基準法の3つの目的
- 安全性の確保:地震や火災に強い建物を実現
- 衛生環境の保持:採光・換気など健康的な居住環境を確保
- 市街地環境の保全:過密な建築を防ぎ、良好な街並みを維持
建ぺい率とは?敷地をどれだけ建物で覆えるか
建ぺい率の定義
建ぺい率とは、敷地面積に対する建築面積の割合のことです。簡単に言えば、「土地を真上から見たとき、建物がどれだけの面積を占めているか」を示す指標です。
📐 建ぺい率の計算式
✅ 具体例:建ぺい率60%の場合
敷地面積:200㎡(約60坪)
建ぺい率:60%
建築可能面積:200㎡ × 60% = 120㎡(約36坪)
→ 1階の床面積を最大120㎡まで建築できます
建ぺい率の制限値
建ぺい率は用途地域ごとに上限が定められています。
| 用途地域 | 建ぺい率の上限 |
|---|---|
| 第一種低層住居専用地域 | 30%、40%、50%、60% |
| 第二種低層住居専用地域 | 30%、40%、50%、60% |
| 第一種中高層住居専用地域 | 30%、40%、50%、60% |
| 第二種中高層住居専用地域 | 30%、40%、50%、60% |
| 第一種住居地域 | 50%、60%、80% |
| 第二種住居地域 | 50%、60%、80% |
| 準住居地域 | 50%、60%、80% |
| 近隣商業地域 | 60%、80% |
| 商業地域 | 80% |
| 準工業地域 | 50%、60%、80% |
| 工業地域 | 50%、60% |
| 工業専用地域 | 30%、40%、50%、60% |
⚠️ 建ぺい率の緩和規定
以下の条件を満たす場合、建ぺい率が緩和されます:
- 角地の緩和:特定行政庁が指定する角地の場合、建ぺい率に10%加算
- 防火地域内の耐火建築物:防火地域内で耐火建築物を建てる場合、建ぺい率に10%加算
- 両方該当:両方の条件を満たす場合、合計20%加算可能
- 建ぺい率80%の商業地域内:防火地域内の耐火建築物なら建ぺい率100%(建ぺい率制限なし)
容積率とは?敷地に対してどれだけの建物が建てられるか
容積率の定義
容積率とは、敷地面積に対する延べ床面積の割合のことです。建物全体のボリュームを制限する重要な指標です。
📐 容積率の計算式
※延べ床面積:各階の床面積を合計したもの
✅ 具体例:容積率200%の場合
敷地面積:200㎡(約60坪)
容積率:200%
建築可能な延べ床面積:200㎡ × 200% = 400㎡(約121坪)
→ 例えば、1階120㎡ + 2階120㎡ + 3階120㎡ = 360㎡の3階建てが可能
容積率の制限値
容積率も用途地域ごとに上限が定められています。
| 用途地域 | 指定容積率の例 |
|---|---|
| 第一種低層住居専用地域 | 50%、60%、80%、100%、150%、200% |
| 第二種低層住居専用地域 | 50%、60%、80%、100%、150%、200% |
| 第一種中高層住居専用地域 | 100%、150%、200%、300%、400%、500% |
| 第二種中高層住居専用地域 | 100%、150%、200%、300%、400%、500% |
| 第一種住居地域 | 100%、150%、200%、300%、400%、500% |
| 第二種住居地域 | 100%、150%、200%、300%、400%、500% |
| 準住居地域 | 100%、150%、200%、300%、400%、500% |
| 近隣商業地域 | 100%、150%、200%、300%、400%、500% |
| 商業地域 | 200%、300%、400%、500%、600%、700%、800%、900%、1000%、1300% |
| 準工業地域 | 100%、150%、200%、300%、400%、500% |
| 工業地域 | 100%、150%、200%、300%、400% |
| 工業専用地域 | 100%、150%、200%、300%、400% |
前面道路による容積率の制限
敷地が接する道路の幅員によって、容積率がさらに制限される場合があります。これを前面道路制限といいます。
📐 前面道路制限の計算式
法定乗数:
・住居系用途地域:4/10(0.4)
・その他の地域:6/10(0.6)
✅ 前面道路制限の具体例
条件:
・第一種低層住居専用地域(住居系)
・指定容積率:200%
・前面道路の幅員:4m
計算:
前面道路制限 = 4m × 0.4 = 160%
結果:
指定容積率200% と 前面道路制限160% の小さい方が適用されるため、
→ 実際の容積率は160%となります
⚠️ 前面道路が12m以上の場合
前面道路の幅員が12m以上ある場合、前面道路制限は適用されず、指定容積率がそのまま適用されます。
高さ制限:建物の高さを制限する4つのルール
建築基準法では、建物の高さについても様々な制限があります。
① 絶対高さ制限(第一種・第二種低層住居専用地域)
第一種・第二種低層住居専用地域では、建物の高さは10mまたは12mに制限されます(都市計画で定められます)。
② 道路斜線制限
前面道路の反対側の境界線から、一定の勾配で引いた斜線の内側に建物を収める必要があります。
📏 道路斜線制限の勾配
- 住居系用途地域:1.25
- その他の地域:1.5
③ 隣地斜線制限
隣地境界線から、一定の高さを超えた部分について斜線制限がかかります。
📏 隣地斜線制限の基準
- 第一種・第二種低層住居専用地域:制限なし(絶対高さ制限のため)
- その他の住居系:20m + 1.25の勾配
- その他の地域:31m + 2.5の勾配
④ 北側斜線制限
北側の隣地への日照を確保するため、北側に対して斜線制限がかかります。
📏 北側斜線制限(対象地域)
- 第一種・第二種低層住居専用地域
- 第一種・第二種中高層住居専用地域
- 田園住居地域
接道義務:建築物を建てるための道路条件
接道義務とは?
建築物の敷地は、原則として幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならないという規定があります。
⚠️ 建築基準法上の「道路」とは?
建築基準法第42条に定める道路のことで、以下のものが該当します:
- 道路法による道路(国道、都道府県道、市町村道など)
- 都市計画法、土地区画整理法等による道路
- 建築基準法が適用された際に既に存在していた道(既存道路)
- 特定行政庁が指定した道(位置指定道路など)
- 幅員4m未満でも一定の基準を満たした道(2項道路)
2項道路(セットバック)
幅員4m未満の道路でも、建築基準法施行前から建物が建ち並んでいた道は、道路の中心線から2mの線を道路境界線とみなします。これを2項道路といいます。
🚗 セットバックとは?
2項道路に接する敷地では、道路中心線から2m後退した線が道路境界線とみなされます。この後退部分をセットバックといい、この部分には建物を建てることができません。
✅ セットバックの具体例
条件:
・前面道路の幅員:3m
・敷地面積:100㎡
セットバック:
道路中心から2m後退 → (4m - 3m) ÷ 2 = 0.5m後退
結果:
セットバック部分は敷地面積に算入できず、建ぺい率・容積率の計算から除外されます
不動産取引における重要事項説明のポイント
宅地建物取引業法による説明義務
不動産を購入する際、宅地建物取引士は以下の事項を重要事項として説明しなければなりません。
- 建ぺい率・容積率:指定された建ぺい率と容積率の数値
- 前面道路との関係:前面道路の幅員と接道状況
- 高さ制限:絶対高さ制限、斜線制限の内容
- セットバックの要否:2項道路に接する場合のセットバック
- 建築確認の要否:建築確認申請が必要かどうか
購入前にチェックすべきポイント
🔍 不動産購入時の確認事項
- 建ぺい率・容積率:どの程度の建物が建築可能か
- 前面道路の幅員:容積率の前面道路制限を確認
- 接道状況:建築基準法上の道路に2m以上接しているか
- セットバックの有無:2項道路の場合の後退距離
- 高さ制限:希望する建物の高さが実現可能か
- 既存不適格建物:現況が法令に適合しているか
既存不適格建物とは?
建築時には法令に適合していたものの、その後の法改正により現行法に適合しなくなった建物を既存不適格建物といいます。
⚠️ 既存不適格建物の注意点
- 建物をそのまま使用することは可能
- 大規模な増改築を行う場合は、現行法に適合させる必要がある
- 建て替える場合は、現行法の基準で建築しなければならない
- 建て替えると以前より小さな建物しか建てられない可能性がある
よくある質問(FAQ)
Q1: 建ぺい率60%、容積率200%の土地で、どんな建物が建てられますか?
A: 敷地面積が200㎡の場合、建築面積は最大120㎡、延べ床面積は最大400㎡です。例えば、1階120㎡ + 2階120㎡ + 3階120㎡ = 360㎡の3階建てなどが可能です。ただし、高さ制限や斜線制限も考慮する必要があります。
Q2: 前面道路が狭いと、指定容積率より小さくなるのですか?
A: はい。前面道路の幅員によっては、指定容積率より厳しい制限がかかります。住居系地域で前面道路4mの場合、容積率は最大160%となり、指定容積率が200%でも実際は160%が上限になります。
Q3: セットバックした部分は、駐車場として使えますか?
A: 可能です。セットバック部分には建物や塀などの工作物は建てられませんが、舗装して駐車場として使用することは問題ありません。ただし、道路としての機能を妨げないことが条件です。
Q4: 角地の建ぺい率緩和は、必ず適用されるのですか?
A: いいえ。角地の緩和は、特定行政庁が指定した角地に限られます。すべての角地が対象になるわけではないので、自治体の建築指導課等で確認が必要です。
Q5: 既存不適格建物を購入する際の注意点は?
A: 将来的な建て替え時に、現在と同じ規模の建物が建てられない可能性があります。購入前に、現行法でどの程度の建物が建築可能か確認することをお勧めします。また、住宅ローンの審査が厳しくなる場合もあります。
まとめ:建築基準法を理解して賢い不動産選びを
建築基準法は、不動産の価値と活用可能性を大きく左右する重要な法律です。この記事で解説した主なポイントをまとめます。
📌 重要ポイントまとめ
- 建ぺい率:敷地に対する建築面積の割合(土地を建物でどれだけ覆えるか)
- 容積率:敷地に対する延べ床面積の割合(建物のボリューム)
- 前面道路制限:道路幅員により容積率がさらに制限される場合がある
- 高さ制限:絶対高さ、斜線制限で建物の高さが制限される
- 接道義務:幅員4m以上の道路に2m以上接する必要がある
- セットバック:2項道路では道路後退が必要
不動産購入時は、これらの制限をしっかり理解し、将来の活用計画に支障がないか確認することが大切です。専門的な判断が必要な場合は、建築士や不動産の専門家に相談しましょう。
🏠 不動産に関するご相談はオッティモへ
建築基準法や建築規制について、専門スタッフが丁寧にご説明します。
建ぺい率・容積率の計算から建築プランまで、ワンストップでサポートいたします。
創業35年の実績と信頼。まずは無料相談からお気軽にどうぞ。
📞 お電話:平日9:00〜18:00 ✉️ メール・チャット:24時間受付
📚 関連記事
- 【重説シリーズ①】都市計画法とは?開発許可・用途地域をわかりやすく解説
- 【次回予告】市街化調整区域での建築:許可基準と手続きを徹底解説|重説シリーズ③
- 【次回予告】用途地域完全ガイド:13種類の特徴と建築制限|重説シリーズ④
❓ よくある質問(FAQ)
空き家を売却する際に必要な書類は何ですか?
空き家を売却する際には、以下の書類が必要です:
- 登記済権利証または登記識別情報
- 固定資産税納税通知書
- 建物の図面や測量図
- 身分証明書
査定にはどのくらいの時間がかかりますか?
通常、現地調査を含めて1〜3営業日で査定結果をご報告いたします。お急ぎの場合は、最短即日での査定も可能です。